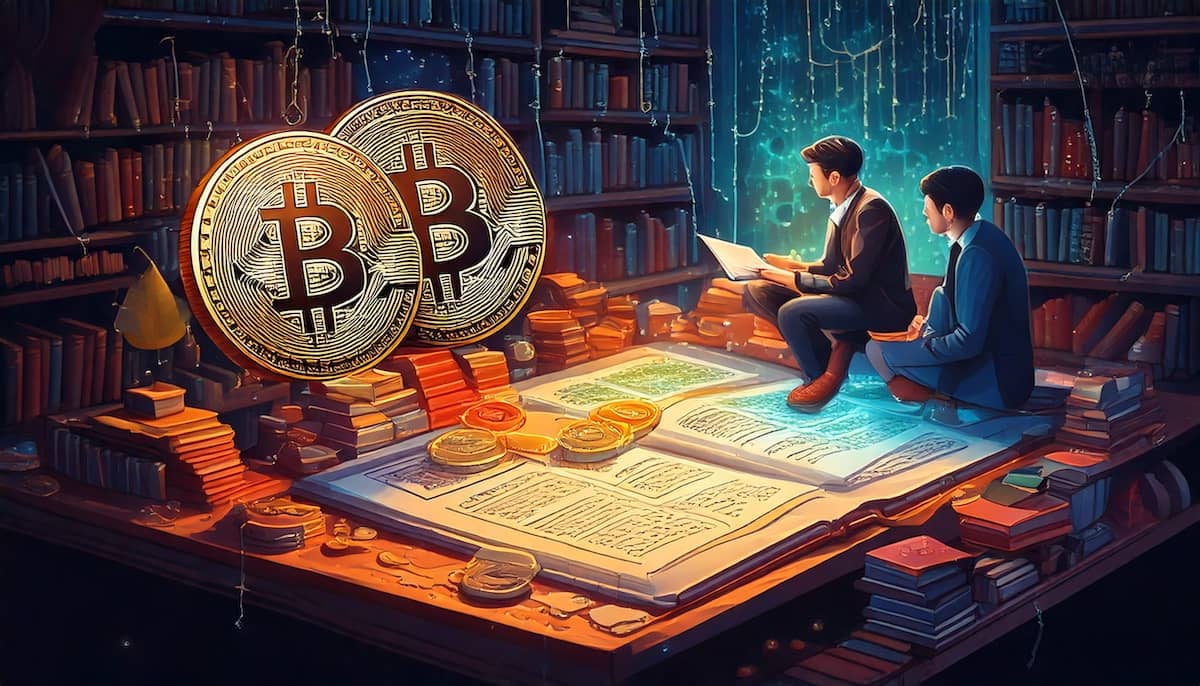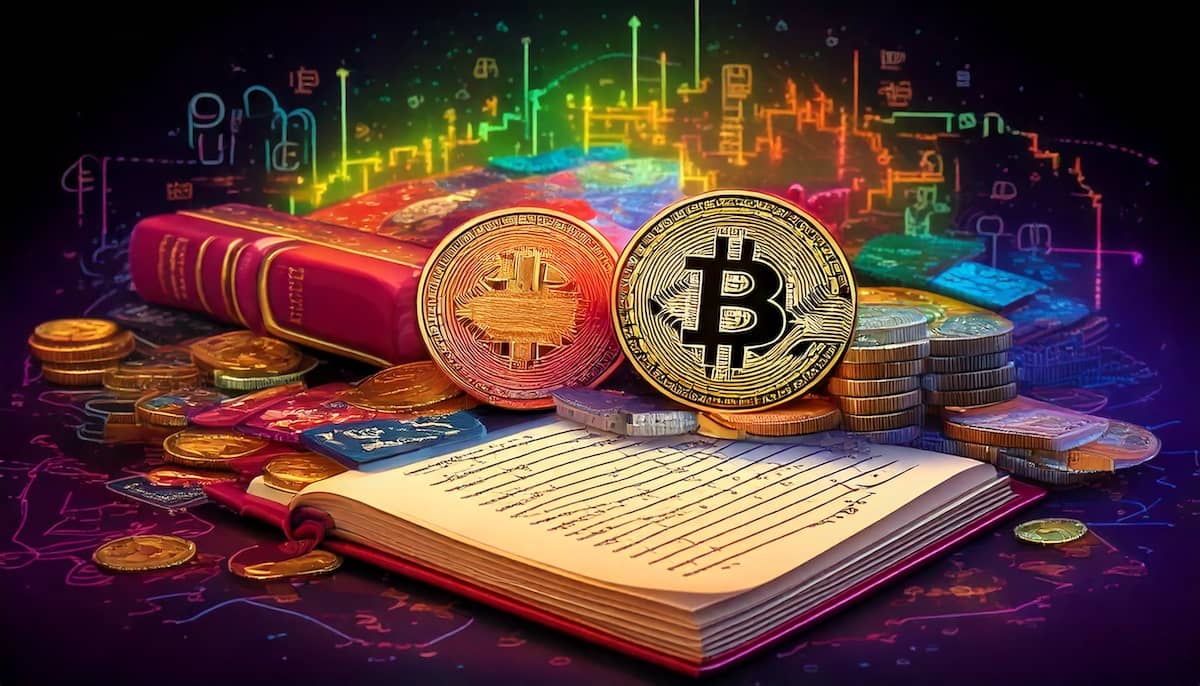ビットコインの価格はトランプ政権誕生後、急騰と急落を繰り返しており、多くの投資家が利益確定の時期を検討しています。しかしビットコインの税率について正しい知識がないまま取引を続けると、思わぬ追徴課税や税務調査のリスクに直面する可能性があります。
本記事では、ビットコインの税率や税金について正しく理解して頂くために、具体的な計算方法から確定申告の手順まで、わかりやすく解説していきます。これらの知識を身につけることで税金の適切な管理が可能になり、安心してビットコイン投資を続けることができます。
ぜひ最後までお読みいただき、確実な税務対策にお役立てください。
ビットコインの税金制度と税率の基本
まずはビットコイン(BTC)にかかる税金と税率の仕組みについて解説していきます。
仮想通貨の所得区分と雑所得の税率
ビットコインや草コインなどの暗号資産(仮想通貨)取引で得た利益は、税法上「雑所得」として扱われ、税率が算出されます。これは、所得税法が所得を10種類に分類しており、仮想通貨による所得が他の区分に該当しないためです。
雑所得は、他の所得区分に当てはまらない所得を幅広く扱う区分です。
仮想通貨の所得には、所得税と住民税が課されます。所得税の税率は、課税所得に応じて5%から45%の累進税率が適用され、住民税率は一律10%です。そのため、ビットコインの所得には最大55%の税率が課せられる可能性があります。
以下は仮想通貨(ビットコイン)の税率一覧になります。
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 194万9000円まで | 5% | 10% | 15% |
| 329万9000円まで | 10% | 10% | 20% |
| 694万9000円まで | 20% | 10% | 30% |
| 899万9000円まで | 23% | 10% | 33% |
| 1799万9000円まで | 33% | 10% | 43% |
| 3999万9000円まで | 40% | 10% | 50% |
| 4000万円以上 | 45% | 10% | 55% |
一方、仮想通貨取引が事業として認められる場合、所得区分は「事業所得」となる可能性があります。
仮想通貨が事業所得として認められる要件は以下の通りです。
- 収入金額が年300万円を超える:仮想通貨取引による年間の収入金額が300万円を超えることが必要。これは利益ではなく、売却額合計を指す
- 帳簿書類の保存がある:取引年月日、取引内容、取引金額などを記録した帳簿書類を保存していることが求められる。事業所得として申告するための重要な要件
- 社会通念上の事業として認められる:仮想通貨取引が継続的かつ反復的に行われ、独立して行われていることが求められる
事業所得では経費として認められる範囲が広がるため、税負担を軽減できる可能性があります。ミームコインなど急騰可能性のある銘柄を保有している人は知っておくべきでしょう。今後が期待されるIOSTも初期に急騰を経験した銘柄ですが、大きく稼いだ日本人が高額な納税を行ったことが報じられており、適切な範囲の節税策は大事と言えます。
総合課税による最大55%の所得税率
仮想通貨の所得が雑所得として課税される場合、総合課税が適用されます。総合課税とは、給与所得や事業所得など他の所得と合算して所得税額を計算する方式です。所得税法では、個人の所得を総合的に捉えて課税することを原則としています。
例えば、年間の給与所得が400万円、ビットコイン取引による所得が300万円の場合、合計所得金額は700万円となります。この場合、所得税率は20%となり、ビットコインの所得300万円に対して所得税と住民税を合わせて約90万円の税金がかかります。
| 年間給与所得 | 400万円 |
|---|---|
| ビットコイン取引による所得 | 300万円 |
| 合計所得金額 | 700万円 |
| 所得税率 | 20% |
| 税金(所得税・住民税) | 約90万円 |
このように、仮想通貨(ビットコイン)の所得は他の所得と合算されるため、高い税率が適用される可能性がある点に注意が必要です。
ビットコインの税金計算の具体的方法
ここからはビットコインの税金計算を具体的にどうすればいいのかをご紹介。ビットコインや仮想通貨の売買損益を計算する際、日本では「総平均法」と「移動平均法」の2つの方法が利用されます。ビットコイン取引の確定申告ではどちらかを用いて計算することになります。
総平均法
総平均法は、1年間に購入した仮想通貨の平均取得価格を基に、売却時の所得を計算する方法です。この方法では1年間の全ての購入取引を集め、平均取得価額を算出します。
具体的には、以下の手順で計算します。
- 購入取引の集計:1年間に購入した全ての仮想通貨の数量と購入価格を集める
- 平均取得価格の計算:総購入金額を総購入数量で割ることで、平均取得価格を算出する
- 所得の計算:売却時の価格から平均取得価格を引くことで、所得を計算する
例えば、以下のようなビットコイン取引を行った場合の所得計算を考えてみましょう。
- 2月:1BTCを200万円で購入
- 7月:1BTCを240万円で購入
- 9月:2BTCを250万円で売却
この場合、総平均法で所得を計算する手順は以下の通りです。
まずは購入数量と購入価格の集計を行います。
- 総購入数量:2BTC
- 総購入価格:200万円 + 240万円 = 440万円
次に、平均取得価格の計算です。
- 平均取得価格 = 総購入価格 / 総購入数量 = 440万円 / 2BTC = 220万円/BTC
最後に、所得の計算をします。
- 売却価格:2BTC × 250万円 = 500万円
- 取得価額合計:2BTC × 220万円 = 440万円
- 所得:500万円 – 440万円 = 60万円
このように、総平均法は1年間の全ての取引を一括して計算するため、複数回の取引を行う場合でも比較的簡単に所得を算出できます。
移動平均法
日本でのビットコインの税金計算には、移動平均法がよく利用されます。この方法は、仮想通貨を購入する都度、その取得価額を計算するものです。ここでは、移動平均法の具体的な計算方法と仮想通貨の税金シミュレーションを紹介します。
例えば、以下のようなシナリオを考えてみましょう。
- ビットコイン1枚を100万円で購入
- ビットコイン1枚を200万円で購入
- ビットコイン2枚を400万円で売却
この場合、移動平均法で取得単価を計算すると、最初の購入時点では取得単価は100万円、2回目の購入時点では総購入額300万円を総購入数量3枚で割り、取得単価は100万円です。ただし、売却時には最初の2枚の取得単価を平均化して150万円とします。
売却金額400万円から取得単価150万円×2枚=300万円を引くと、利益は100万円になります。
このように、移動平均法は実際の取引状況に近い形で取得価額を把握できるため、年度途中での見積もりが容易です。
総平均法と移動平均法はどちらがおすすめ?
どちらを選ぶかは、以下の点を考慮してください。
- 取引回数が多い場合:総平均法が計算しやすい
- 価格変動が激しい場合:移動平均法がリアルタイムに反映できるため、有利
一度選んだ計算方法は3年間変更できないため、慎重に選択することが重要です。
| 計算方法 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 総平均法 | 期間内全体の購入金額を購入数量で割り、平均取得単価を算出 | 簡単だが、年末まで見積もりが難しい |
| 移動平均法 | 仮想通貨を購入する度に取得価額を計算 | 手間がかかるが、期中でも見積もり可能 |
ビットコインの利益計算ツールの活用
ビットコインの税金計算方法が分かっても、実行に移すのは容易では無いことは想像に固くないでしょう、ビットコインの税金計算を効率化するには、利益計算ツールの活用が欠かせません。特に仮想通貨のプレセールに参加した場合、取引履歴は複雑になりやすく、手計算ではミスが起こる可能性があります。
以下は日本国内で、ビットコインやアルトコインの確定申告での税金計算によく使われる計算ツールになります。
| ツール名 | 主な機能 | 対応取引所 |
|---|---|---|
| Gtax | 取引履歴をアップロードして損益を自動計算 | 国内外多数の取引所 |
| クリプタクト | 多数の取引所とAPI連携し、ICOにも対応 | Binance、POLONIEXなど |
これらのツールは日本の税制に適合した利益計算をサポートしており、日本国内の税理士が関与しているため、日本での仮想通貨の確定申告に適しています。
ただし、対応取引所や無料利用範囲がツールごとに異なるため、自分の取引状況に合ったものを選びましょう。
ビットコインの課税対象取引
ビットコイン取引は利益を得る機会であると同時に、税金が発生する場面でもあります。仮想通貨取引で得た利益は、所得税の課税対象となる雑所得に分類され、総合課税として扱われます。
これは、給与所得など他の所得と合算して税額が計算される仕組みで、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税制度が適用されます。そのため、ビットコイン取引を行う際には、どの取引が課税対象となるのかを正しく理解することが重要です。
ここでは以下の3つを紹介します。ビットコインのマイニングでも税金が発生する場合がありますが、特殊なためここでは割愛します。
- 日本円への換金時の課税判断
- 仮想通貨間の交換における税金
- 物品購入時の課税ポイント
日本円への換金時の課税判断
ビットコインを日本円に換金した場合、その時点で利益が出ていれば課税対象となります。日本円への換金は、ビットコインの売却とみなされるためです。
具体的には、ビットコインの売却価額から取得時の「取得単価」を差し引いた金額が利益となり、この利益に対して税金が課せられます。
以下は日本円への換金時の利益計算例です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 取得価格 | 100万円 |
| 売却価格 | 400万円 |
| 利益(課税対象) | 300万円 |
取得単価の計算方法には前述の「総平均法」と「移動平均法」があります。どちらを選ぶかによって利益額が変動する可能性があるため、慎重に選択する必要があります。換金は仮想通貨取引における基本的な課税対象取引として認識しておきましょう。
仮想通貨間の交換における税金
ビットコインを別の仮想通貨に交換した場合も、税金が発生する可能性があります。この場合、ビットコインを一度売却し、その売却代金で別の暗号資産を購入したとみなされるため、ビットコインの売却益に対して課税されます。
具体例として、仮想通貨間の交換時の利益計算をしてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 取得価格 | 100万円 |
| 売却価格 | 200万円 |
| 利益(課税対象) | 100万円 |
例えば、1BTCを100万円で購入し、その後1BTCが200万円に値上がりしたタイミングでイーサリアム(ETH)に交換した場合、100万円の利益が課税対象となります。仮想通貨間の交換は日本円が介在しないため課税対象と認識しにくいですが、税法上はビットコインの売却として扱われるため注意が必要です。
2019年に日本国内でビットコインをリップル(XRP)に変換し、申告の必要性を知らず無申告だったサラリーマンの男性に、2億円以上の追徴課税が課されています。
物品購入時の課税ポイント
ビットコインで商品を購入した場合も課税対象となることがあります。ビットコインを物品購入の決済手段として利用した場合、その時点でビットコインを売却したとみなされるためです。
物品購入時の利益計算例を見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 取得価格 | 100万円 |
| 時価(購入時) | 150万円 |
| 利益(課税対象) | 50万円 |
例えば、1BTCを100万円で購入し、その後1BTCが150万円に値上がりしたタイミングで150万円相当のパソコンを購入した場合、50万円の利益が課税対象となります。
物品購入にビットコインを利用することは日常生活における仮想通貨の利用シーンとして考えられますが、税金が発生するタイミングとして認識しておく必要があります。
サラリーマンにおけるビットコインの確定申告
ここからは該当者が多いであろう「会社員・サラリーマンの場合のビットコインの確定申告」について見ていきます。
会社員の確定申告必要額の基準
会社員がビットコイン取引で利益を得た場合、一定の条件下で確定申告が必要です。原則として、年間の給与収入が2000万円以下で、給与所得以外の所得が20万円を超える場合に確定申告が求められます。
この「給与所得以外の所得」には、ビットコイン取引で得た利益も含まれます。
特に注意すべき点は、住民税の申告です。所得税では20万円以下の所得は申告不要ですが、住民税では金額に関係なく申告が必要となる場合があります。
- 給与以外の所得がある場合:給与以外の所得がある場合、住民税の申告が必要。所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は別途必要
- 年末調整を受けていない所得がある場合:年末調整を受けていない所得が20万円以下でも、住民税の申告が必要
- 控除の変更がある場合:医療費控除や生命保険料控除などの控除を追加する場合、住民税の申告が必要
これらの条件に該当する場合、所得の金額に関係なく、住民税の申告が必要です。そのため、少額の利益でも住民税の申告を忘れないようにしましょう。
確定申告を適切に行うことで、税務署とのトラブルを防ぎ、安心して仮想通貨取引を続けることができます。
サラリーマンの申告書提出方法
確定申告が必要な場合、給与所得者は確定申告書を作成し、税務署に提出します。提出方法は以下の3つがあります。
- e-Taxを利用したオンライン提出:自宅から簡単に申告手続きを完了できる
- 郵送による提出:税務署に出向く必要がなく、都合の良い時間に手続き可能
- 税務署窓口への直接持参:職員に相談しながら手続きを進めたい方に適している
確定申告書の作成には、国税庁の「確定申告書作成コーナー」が便利です。必要事項を入力するだけで税額が自動計算されます。
また、スマートフォンを使った「スマホ申告」も可能で、マイナンバーカードがあれば手軽に申告を完了できます。
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。期限内に余裕を持って手続きを行いましょう。
無申告時の追徴課税制度
確定申告を怠った場合や期限を過ぎた場合、追徴課税が課される可能性があります。追徴課税には以下の2種類があります。
- 加算税:納めるべき税額に追加されるペナルティ。期限内に申告しなかった場合に課され、税額の15%(50万円を超える部分は20%)が適用される
- 延滞税:納付が遅れた日数に応じて課される利息のようなもの
これらの追徴課税は、意図的な脱税でなくても課される可能性があり、納税者にとって大きな負担となります。税務署は仮想通貨取引所のデータやブロックチェーンの記録を活用して取引状況を把握しており、無申告が発覚する可能性は高いです。
また2027年より国税局は、海外の本人確認なしの取引所を利用した脱税を取り締まるため、海外当局との連携も予定しています。
申告漏れに気づいた場合は、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告を行うことで、加算税を軽減できる場合があります。仮想通貨の税金に抜け道は無いため、正確な申告を心がけ、トラブルを未然に防ぎましょう。
サラリーマンのビットコイン取引にかかる税金例(簡易計算)
ここではざっくりとサラリーマンのビットコインにかかる税金がどれほどか、表形式でまとめてみました。あくまで簡易計算でのサラリーマンの事例になるので、各個人にかかる正確な税金は、計算ツールなどで算出してください。
| 年収 | 利益30万 | 利益120万 | 利益250万 |
|---|---|---|---|
| 400万 | 9万 | 36万 | 75万 |
| 500万 | 9万 | 36万 | 82.5万 |
| 600万 | 9万 | 39.6万 | 82.5万 |
| 700万 | 9.9万 | 39.6万 | 107.5万 |
| 800万 | 9.9万 | 51.6万 | 107.5万 |
| 900万 | 12.9万 | 51.6万 | 107.5万 |
| 1,000万 | 12.9万 | 51.6万 | 107.5万 |
ビットコインの税務戦略
ここからはビットコインの税金に対して取れる対策を解説していきます。以下の3つの視点を紹介します。
- デジタル取引記録の管理を徹底する
- 税務専門家への相談
- 法人化による税負担の最適化
デジタル取引記録の管理を徹底する
ビットコインを含む仮想通貨取引では、日々のデジタル取引記録を適切に管理することが非常に重要です。仮想通貨取引で得た利益は課税対象となるため、正確な記録が納税額を正しく計算するための基盤となります。
具体的には年間の取引履歴を詳細に記録し、総平均法や移動平均法といった方法で取得単価を計算する必要があります。これらの計算方法は国税庁でも推奨されており、計算ツールや計算用ファイルが提供されています。
また、一部の取引所では年間取引報告書を発行してくれる場合もあるため、これを活用することで計算の手間を軽減できます。
ビットコインの取引記録を正確に管理することで、税務申告時の計算ミスを防ぎ、スムーズな税務処理が可能になります。ビットコインの税率や税金計算はもちろん、新しい仮想通貨の場合は計算が煩雑になりやすいです。
正確に把握するためにも、記録の管理は欠かせません。
税務専門家への相談
ビットコインの税金や税率に関する疑問や不安がある場合、早めに税務専門家へ相談することが重要です。仮想通貨税制は複雑で、取引内容や状況によって税務上の解釈や計算方法が異なることがあります。
例えば、取引量が多い方や複雑な取引を行っている方、また税法に詳しくない方は、税理士などの専門家に相談することで適切なアドバイスを受けられます。税務専門家は、仮想通貨の税金計算や確定申告書の作成支援を行い、税務リスクを軽減するサポートをしてくれます。
特に、初めてビットコインの確定申告を行う場合や、仮想通貨の税率が変わる可能性がある場合には、専門家の助けを借りることで手続きをスムーズに進めることができます。
以下の表に、目安料金を簡単にまとめます。
| 依頼内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 取引件数が少ない場合 | 5万円〜10万円 |
| 取引件数が100件〜1000件 | 10万円〜20万円 |
| 取引件数が1000件以上 | 20万円〜50万円以上 |
| 月額顧問料 | 1万円〜3万円 |
| スポット依頼料 | 1万円〜3万円 |
記帳代行を含む場合、総額8万円〜25万円程度になることもあります。
法人化による税負担の最適化
ビットコイン取引で得る所得が多額になる場合、法人化を検討することで税負担を最適化できる可能性があります。個人と法人では適用されるビットコイン税率や税制上の優遇措置が異なるため、法人化によって税金面でのメリットを享受できる場合があります。
- 個人:所得税と住民税を合わせて最大55%の税率がかかる
- 法人:最高税率は約35%(法人税23.2% + 住民税など約10%)で、個人よりも低くなる
| 法人所得金額 | 法人税率 |
|---|---|
| 800万円以下 | 約15%~19% |
| 800万円超 | 約23%~25% |
例えば、仮想通貨取引で年間1億円の利益を得た場合、個人としては所得税と住民税を合わせて最大55%のビットコイン税率が適用され、約5500万円の税金がかかります。一方、法人化すると最高税率が約35%となり、約3500万円の税金で済むため、約2000万円の節税効果が期待できます。
仮想通貨取引における法人税の最高税率は個人より低いですが、法人設立には初期費用や手間がかかり、法人運営には会計処理や税務申告などの負担が伴います。そのため、法人化を検討する際には、仮想通貨取引の規模や将来の事業展開を考慮し、税務専門家と相談しながら慎重に判断することが必要です。
仮想通貨の税制改正と最新動向
近年日本でもビットコインを含めた仮想通貨の税制が積極的に議論されており、ビットコイン取引における税金・税率がポジティブな方向で変わる見込みです。ここではビットコインの税率に関する最新の動向を共有します。
仮想通貨の税制改正における重要ポイント
仮想通貨(ビットコイン)の税制改正において、特に重要なのは所得区分と税率です。現在、個人のビットコイン取引による所得は「雑所得」に区分され、総合課税の対象となっています。この方式では、給与所得など他の所得と合算して税額が計算され、所得が大きくなるほど税率が高くなる累進課税制度が適用されます。
| 税区分 | 税率(所得税) | 税率(住民税) | 合計税率(最大) |
|---|---|---|---|
| 雑所得 | 5%~45% | 10% | 最大55% |
2022年12月には、ビットコイン取引における事業所得の取り扱いが変更されました。年間収入が300万円を超え、帳簿書類を保存している場合、事業所得として認められる可能性があります。
事業所得として認められると、必要経費の範囲が広がり、青色申告特別控除などの特例も適用可能です。これにより、税負担を軽減できる場合があります。
申告分離課税への移行に関する展望
現在ビットコイン取引で得た利益は総合課税の対象ですが、株式やFXなどの金融商品取引では一律20.315%の申告分離課税が適用されています。この違いから、「ビットコインの税金は高い」と感じる方も多いでしょう。
業界団体である一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)は、仮想通貨取引による所得を申告分離課税とするよう政府に要望しています。申告分離課税が導入されれば、所得が増えても税率が一定であるため、税負担が軽減される可能性があります。
また、投資家にとって税務上の予測がしやすくなり、仮想通貨市場の活性化も期待されます。
現時点では仮想通貨の申告分離課税への移行は実現していませんが、海外の税制事例や業界団体の働きかけを考慮すると、今後の税制改正で導入される可能性は十分にあります。ビットコインの税率・税金制度が変わる可能性に備え、仮想通貨の分離課税はいつからなのか、最新の動向を注視することが重要です。
まとめ
本記事では、ビットコインの税率について、所得区分から具体的な計算方法まで詳しく解説しました。ビットコインの利益は原則として雑所得として申告が必要で、他の所得と合算して総所得金額に応じた税率(5%〜45%)が適用されます。
しかし、2025年度税制改正大綱には「暗号資産の税制見直し検討」が明記されており、金融庁は2025年6月末を目処に制度の検証を行う予定です。今後株式と同様の20%の一律分離課税が仮想通貨にも適用されることで、ビットコインの税率は今より下がる可能性が高く、注目を集めています。
これにより、日本国内でのビットコインETFの進展にも期待が寄せられています。
1000倍仮想通貨のような急騰銘柄の売却にかかる税率が下がることで、日本国内でも投資熱が高まることが予想されます。本サイトでおすすめしている仮想通貨への投資を考えている人は、ビットコイン含む仮想通貨の税率に関する最新情報も追っておくようにしましょう。