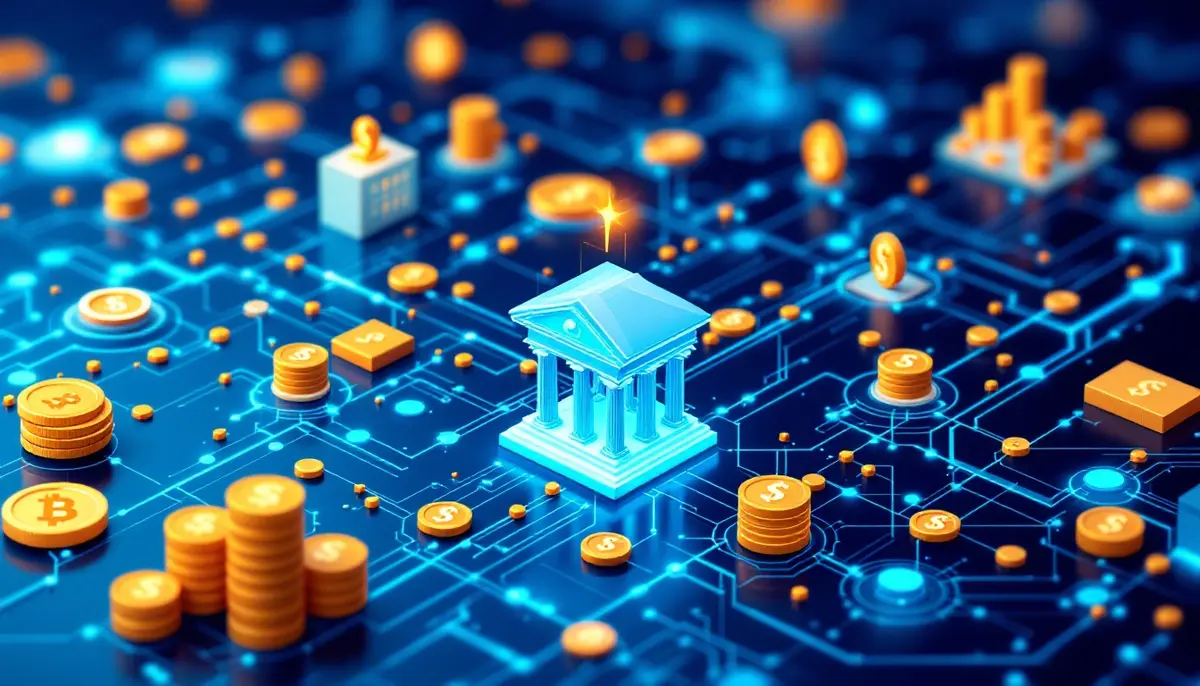米大手銀行のJPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シティグループなどは23日、規制準拠型ステーブルコインの共同発行について初期段階の協議を開始したことが明らかになった。
銀行コンソーシアムによるステーブルコイン構想
この取り組みには、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ウェルズファーゴのほか、決済サービスのゼル(Zelle)を運営するアーリー・ワーニング・サービスや、銀行間決済を手がけるザ・クリアリング・ハウスも参加している。
各機関は、暗号資産(仮想通貨)分野の分散型ステーブルコインやフィンテック主導の代替手段に対抗できる、規制に準拠した相互運用可能なデジタル通貨の創設を目指している。
検討中のモデルでは、他の銀行もこのステーブルコインプラットフォームに参加でき、金融機関間の取引が可能になる仕組みを想定している。また、地域銀行やコミュニティ銀行向けの別個のコンソーシアム設立についても議論されている。
規制環境の変化が後押し
銀行各社の動きの背景には、立法府での動きがある。上院で審議が進むGENIUS法案は、ステーブルコイン発行者に対する規制を確立し、銀行と非銀行の両方に適用される規則を定めている。
同法案は非金融企業の市場参入を完全に禁止するものではないが、一定の規制枠組みを提供している。
規制当局は2022年以降ステーブルコインに対する監視を強化しており、これが銀行のデジタル資産採用の遅れにつながっていた。しかし、最近の規制明確化により、銀行が積極的に参入を検討する環境が整いつつある。
一方で、テクノロジー大手や小売企業がステーブルコイン市場への無制限アクセスを獲得した場合、預金や決済業務の大きなシェアを奪われる可能性があるとの懸念も銀行側にはある。この競争圧力も、銀行コンソーシアム形成の動機となっている。
現在の協議は抽象的な段階にあり、最終的な構造は決まっていない。初期のアイデアでは、トークン保有者が参加銀行で償還できる許可不要のブロックチェーンシステムが参考にされている。
提案されるトークンは米ドルなどの法定通貨に連動し、機関投資家の幅広い利用を想定している。このプロジェクトの成功により、従来のビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といったデジタル資産との相互運用性も検討されている。